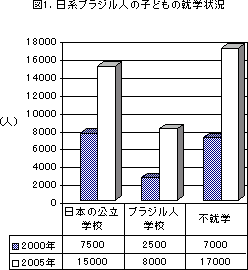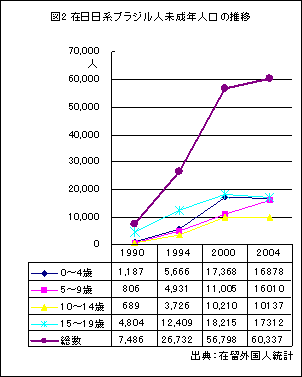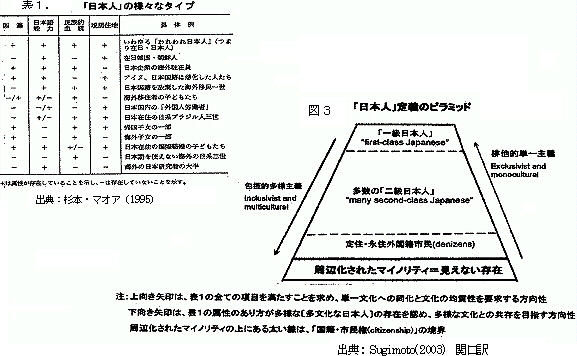|
�w�G�� �C�O���n�l�x��57���i(��)�C�O���n�l���� ���s�A2005�N9��10���j |
|
�ݓ����n�q��̋���Ɠ��{�̊w�Z�F�l�ވ琬�V�X�e���̎��_���� ���m�q�@��R�Z����w ���́A�l�ł͂Ȃ��V�X�e�� |
|
���n�l���N���߂��錻��F�����l�ވ琬�V�X�e���̋@�\�s�S |
|
|
�i�P�j����������s�A�w�Ɓu�j�[�g�v |
|
|
|
�@�ł͌��݁A���肵������@���ۏႳ��Ȃ��܂ܓ� |
|
|
|
|
���Z���m�F�ł����ɏA�w���Ԃ��u�s���v�Ȑ����܂�ł���͂����B�������A�ړ��ɂ���Ď��Ԃ��u�s���v�� |
|
�ԂŐ������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B |
|
|
��5350�l�ŁA�����F�Z30�Z�ɍݐЂ���̂�2545�l���B�������A���F�Z�̍ݐЎ҂́A���w���S�P���A�� |
|
|
|
|
|
�w���T�S���ŁA���Z���͂킸���T���������Ȃ��B�u���Z�̔N��ɂȂ�ƁA�݂ȓ����n�߂Ă��܂��B���ꂪ���� �i�Q�j���{�̌����w�Z�ɂ����錻��F�h���b�v�A�E�g�ƒ�w�� |
|
|
|
�w�����K�v�ȊO���l�������k�v�̐���19,678�l�ł���i�����Ȋw�Ȓ���9�j�B���ʂł́A�|���g�K�� ���{�̊w�Z�V�X�e���̖��F�K�w�i���g��Ɓu��ċ����́v���� |
|
|
|
���J�߂��炢���B���ɂ�����̂Ƃ��Ȃ��Ƃ��ǂ̂悤�ɈႤ���A�ǂ����������邩�Ƃ������Ƃ����e���鋳��J�� |
|
�V�����u�����������v�^��������V�X�e���̍\�z�Ɍ������|Living Together in Cultural Diversity- |
|
|
|
�@���A�}���ȏ��q����Ƒ������E�������Љ���o��������킽�������́A�\�P�Ɍ���悤�� �@�u���{21���I�r�W�����v��咲�����10���`�����ڎw���ׂ����{�̏������́A�u�J���ꂽ���� |
|
���p���� |
|
|
|
|
|
�C�O���n�l����i2003�j�w���n�A�J�Ҏq��̋���Ɋւ�����Ԓ����@���x |