|
一杯のラーメン |
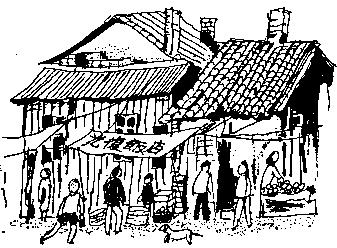 |
|
たっちゃんは、小学校五年生です。たっちゃんの顔は青白くふくらんで、ちょうど御盆に目鼻をつけた顔をしています。いつも体をだるそうに、ぽっつりぽっつり歩きます。 だから、孤児からは、草だんご 草だんごといわれていました。 「おい草だんご、今日のおめえの顔少し、しぼんだようだな」といわれると、とてもうれしい顔をします。 また「なんだ今日の顔 ばかに、まんまるだなあ」というと、とても、心配そうな顔になります。 たっちゃんは、顔のことを友だちからいわれても、あんまり気にかけません。友だちからいわれることで、自分の健康のようすが、わかるからです。たっちゃんは、小さい時から腎臓が悪かったので、死んだお母さんは、朝たっちゃんの顔を見ては、「よかった よかった今日は、顔のむくみがなくなったね」とか、いつも食事のことで、大変苦心していたのを知っていたからです。 「おまえの病気は、塩分が一番いけないんだよ、少しだったらいいんだけどね」と口ぐせのようにいっていました。 そして、うすい味噌汁や塩をぬいた梅干しを食べさせてくれたからです。 たっちゃんは、収容所でも、お母さんから教えていただいたことをよく守って生活をしていました。収容所では、調味料として岩塩を配給してくれましたが、できるだけみんなより少なめに使っていました。 たっちゃんは小さい時からお医者さんから、はげしい運動はとめられていましたから、運動の方は、余り上手ではありません。ですから家の中で、本をよんだり、絵をかいたりして遊んでいました。とくに落語の本が大好きで、同じ本を何回も読んでもあきませんでした。それを見ていた、お父さんやお母さんに、「おまえが、そんなに落語がすきだったら、落語のいい先生について、一生けんめい勉強して、真打ちになって高座で、たっちゃんの落語を聞きたいもんだ」とよく言われていました。たっちゃんも、すっかりその気になっていました。 ですから、たっちゃんは、みんなのまえで、お話をするのが、大好きです。たっちゃんは、たのまれると、みんなの前でおもしろおかしく、身振り手振りをまじえながらお話を始めます。教室の教段まんなかに座り、短い棒を扇子のかわりに持ちぐるっとみんなを見わたすと、「ええ、毎度ばかばかしいお話しを致しますが、嘘をつくとえんま様に舌を抜かれると申しますが、たわいのない嘘をつくというのは、案外かわいらしいものでございます。 むかし むかしあるところに、うそつき村という村がありました。村人たちが、みんなで嘘をつくのをきそいあって楽しんでいました。 その村の近くに、ごんべいという百姓がいました。  おらあこそは、世界一の名人だあ!なんでも、隣村の村長が、うそつきの名人だと村の人からいわれているそうだ。どっちが、ほんとうのうそつきの名人が手合わせしてもらおうと思い、ある天気の良い日に、うそつき村へひょこひょこ歩いて行きました。 うそつき村の近くまで来ると、一人の男の子が魚釣りをしていました。  「おうい!そこのわらしっこ、魚釣れるかあ」というと「ああ、さっき大きな鯨を釣ったけどかわいそうなので、逃がしてやった」といいました。 「おうい!そこのわらしっこ、魚釣れるかあ」というと「ああ、さっき大きな鯨を釣ったけどかわいそうなので、逃がしてやった」といいました。「チエッ!わらしっこのくせに、うめえうそをつくなあ」とごんべえは、心の中で思いました。そこで、負けては、なるものかと、すかさず 「そうかあ、おらあもな昨日、五色沼で釣りをしてたらな、十間程の大きな、なまずが釣れると、天がにわかに、かきくもりムクムクとした真っ黒な雲の中から、おらあ見たことのねえでっけい鷹が、ひょいとなまずをつかむと山奥へはこんでいったあ」とさも得意そうに言いました。「ところでおめえの、おとっつぁんは、どうしているだあ」と聞くと、ごんべえの顔をちょっと見ると、すました顔をして、 「ああ いねえよ、昨日の大風で、富士山がたおれそうになったんで、村の衆と竹ざお持って朝早くつっかえぼうにいったあ」といいました。 これを聞いたごんべいは、びっくりして逃げてかえりました。‥‥‥ このように、たっちゃんは、つぎからつぎへと泉から水がこんこんとわくように、つぎからつぎへと話が出てきます。 話終わった、たっちゃんは、大きな拍手をもらってさも、満足そうにピョコンとおじぎをして、部屋の廊下側の自分の場所へかえっていきます。 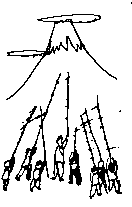 元気だった頃の、たっちゃんは、あっちの部屋、こっちの部屋でひっぱりだこで、難民収容所の人気者でした。 だれからでも、声をかけられると喜んで出かけ、落語や小話をします。なんにも娯楽のない、生きるだけが精一杯の人たちだけの集まりですから、たっちゃんの話は、明かるい生きる喜びのひとときを、みんなに与えたに違いありません。 たっちゃんが元気だったのは、十月初旬まででした。 あれほど気をつけていた腎臓病は、栄養失調と疲れがかさなって、日増しにだんだん悪くなるいっぽうです。起きている時よりも寝ているほうが多くなってきました。 たっちゃんは、体全身むくんでいるようでした。顔を見ると、はれぼったいまぶたの奥の方から、光を失った象の目のように、うつろにのぞいています。 もう、誰が見ても、たっちゃんの命は二・三週間しかもたないように思われました。 大変仲が良かった、おなじ年頃のさんちゃんは、自分のことのように心配しましたが、どうすることも出来ません。 難民収容所には、医務室がありましたが、日本人の医師はたまに来るだけで、しかも顔色をうかがうだけでかえって行きます。医師としても、できるだけ治療してあげたいと思ったに違いありませんが、当時、満州では、終戦後直ちに、ソ連軍に医療施設・薬品を接収されてしまったので医師としてもどうすることも出来なかったのでしょう。ですから、入院してもただ寝かされ、死ぬのを待つばかりの状態であることを、さんちゃんは、よく知っていたのです。 ですから、さんちゃんは、となりにたっちゃんを寝かせ、腰が痛いというと一生懸命腰をなぜてあげたり、水を飲みたいといったら急いで、水を水筒にくんであげて飲ませてあげました。 毎日の食事の用意は、勿論 さんちゃんがしてあげます。たっちゃんの食事は、こうりゃんや粟のおかゆです。こうりゃんや粟のおかゆは、お米のおかゆと違って、燃料と時間がかかります。ですから、さんちゃんにとって大変な仕事です。十月中旬になると燃料になるものが収容所付近には、何も無くなってしまったからです。なぜなら、多くの難民の大人も子供も先をあらそって、燃料にするため、あいている部屋の机や椅子、廊下、窓わくや天井の板なども、てじかにあるもの殆ど燃えるものは、すべて燃料にしてしまいました。 多くの難民たちは、戦火に追われ大変な苦労をしながら、命からがら逃げてきたのです。しかも、逃げる途中で、暴民化した中国人やソ連軍の兵士によって、衣類やお金を取り上げられてしまったのです。ですから、そうするより仕方がなかったのです。 さんちゃんは、収容所から片道五・六キロメートル先の新京郊外へ行ってこえだや枯れ草を取ってきます。たっちゃんの分まで、取らなくてはいけないので週に二・三回いかなくてはいけません。 このようにして、一生けんめい作ってあげたこうりゃんのおかゆもたっちゃんは、一・二度口にするだけで頭を横にふるだけになりました。 さんちゃんは、大きな声で 「たっちゃん!たっちゃん!何をたべてえの、いってくれよ・いってくれよ……」とさんちゃんは、いいながらだんだん泣き声になっていきます。そして、 「食べたいもの、遠慮しないでいいんだよ、たっちゃんとぼくとの仲じゃないか、ねえ、ぼくのいうことわかる?なにかいっておくれよ」というと、 たっちゃんは、なにか、口をモグモグ動かしています。 「たっちゃん、もっと大きい声でいえよ、聞こえないじゃないか、さっきいったように、遠慮しないで」たっちゃんは、小さい声ですまなそうにいいました。 「できたら、わるいけどラーメンを食べたいの」といいました。たっちゃんは、きっと中国のラーメンは塩気が多いので、きっとお母さんに食べさせて貰えなかったのでしょう。だからこの世の別れに一度でよいからラーメンを食べたかったのでしょう。たっちゃんの食べたい物が分かりましたが、ラーメンを買うお金は一銭だって持っていません。どうしたらいいだろう、さんちゃんは、たっちゃんの願いをかなえるために色々考えました。「そうだ!靴下だ、靴下をもって飯店でラーメンと交換してくれるはずだ」 終戦直後の満州では、中国人も日用雑貨や衣料などは、なかなか手にはいりにくく困っていました。ですからたいていのものは、物々交換してくれるのです。  さんちゃんは、急いで靴下をぬぎ始めました。使いふるした靴下なのですが、まだ穴があいていません。だからラーメンと交換してくれるはずだ。そして、たっちゃんにラーメンを食べさせて上げられる。と喜んで外へ出ようとした時、それを見ていたおばさんが言いました。 さんちゃんは、急いで靴下をぬぎ始めました。使いふるした靴下なのですが、まだ穴があいていません。だからラーメンと交換してくれるはずだ。そして、たっちゃんにラーメンを食べさせて上げられる。と喜んで外へ出ようとした時、それを見ていたおばさんが言いました。「さんちゃん、友だちを思う気持ちは、分かるけど今一番大切なことは、自分の体を守ることなの、そして、日本に帰って家族の人や親戚の人を安心させることよ それに、さんちゃんは、満州の虎林で、ソ連軍の戦車攻撃をうけて、お父さんとお母さん、弟までなくしてしまったんでしょう。  さんちゃんが、この冬もしものことがあったら、誰がこのことを日本に帰って話すの?これが、さんちゃんの大切な役目じゃないの、靴下とラーメンとの交換は、やめなさい。 人がいいのもいいかげんにしなさい。私はね、水をさすわけじゃないけど、さんちゃんのことを思って」ここまで、いうとおばさんは、声をひそめさんちゃんの耳元で、 「そういっちゃ悪いけど、たっちゃんは、あの状態じゃ今夜もつかどうか、わかりゃしないよ、さんちゃんのやっていることは、はっきりいって無駄じゃないの」と おばさんは、強い調子でいいました。さんちゃんは、ちょっとたじろぎました。でも、さんちゃんは、はっきり断りました。 「おばさんほんとにありがとう。今、僕にとって大切なのは、たっちゃんの命なんです。一日でも二日でも生きてほしいのです。おばさんが心配してくれた、靴下は、なんとかなると思います。 足にボロ切れを包帯のようにまけば靴下がわりになるし、よくもんだ新聞紙を足にまいて、縄か細ひもでまけばなんとかなります」といっておばさんの方を向いてにこっとほほえみました。そしてはんごうをもって、木枯らしが吹く街へ走って行きました。 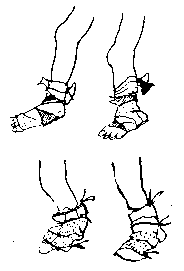 まもなく、さんちゃんがにこにこしながら息をはずませながら、廊下の方から大きな声で「たっちゃん!ラーメンが買えたぞう!ラーメンが買えたぞう!」いいながら帰ってきました、そして、たっちゃんのそばまでくると、 まもなく、さんちゃんがにこにこしながら息をはずませながら、廊下の方から大きな声で「たっちゃん!ラーメンが買えたぞう!ラーメンが買えたぞう!」いいながら帰ってきました、そして、たっちゃんのそばまでくると、「たっちゃん!ラーメンだぞう」と言って、ふたをとってたっちゃんに、においをかがせてあげました。たっちゃんは重そうにまぶたをあげ 「ありがとう、僕のために」といいながら無理をして、起きあがろうとします。さんちゃんは、 「いいんだぞ!寝たままでいいんだぞおう」といってねかせようとしました。 「ううん、きょうはひさしぶりに起きたいの、起きたいの」というので、さんちゃんは、背中と腰を静かに押して起こしてあげました。たっちゃんは、あつぼったいまぶたをあげ見上げていいました。 「病気の僕に、こんなに親切にしてくれてありがとう。ほんとにありがとう‥‥」 たっちゃんの、ふくれあがったまぶたの奥から涙があふれでました。人間の涙ってこんなにあるのかと思うほど涙がつぎからつぎへとあふれでました。 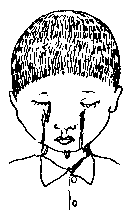 たっちゃんは、深く息を吸って、 たっちゃんは、深く息を吸って、「ぼくは‥ぼくは‥もうたっちゃんにお礼することは、できないでしょう‥‥ごめんなさい」といいながら両手をついて、深く頭を下げさんちゃんにお礼をいいました。 さんちゃんは、びっくりして、「いいんだよ いいんだよラーメン食べて元気になっておくれよ」といって、はんごうのうらぶたに食べやすいように、よそってあげました。 たっちゃんは、うらぶたに、もられたラーメンを重そうにもって つるんと二・三回食べ、汁をおいしそうにごくんと飲み、うらぶたを静かにおきました。 さんちゃんの顔を見て、「こんなに、 おいしいラーメンいままで食べたことなかった。さんちゃんは、お地蔵さまにみえます」といって、両手を合わせ祈るようにいいました。 「どうして、ぼくがお地蔵さまなの」と聞こうとしたときたっちゃんの体が、ぐらっとうしろへ、たおれかけました。「たっちゃん!たっちゃん!死んじゃだめ 死んじゃだめ」といいながら、たっちゃんを静かに横にしてあげました。そして、たっちゃんが大切にしていた軍隊用の毛布をかけてあげました。 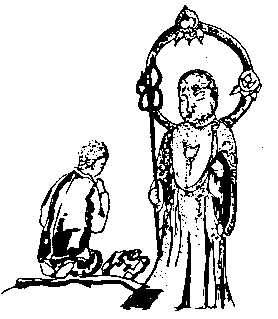 しばらくたって、たっちゃんの顔が少しずつ、あかみがさし、意識がもどったようです。たっちゃんは、うすめをあげ しばらくたって、たっちゃんの顔が少しずつ、あかみがさし、意識がもどったようです。たっちゃんは、うすめをあげ「さんちゃん、心配させてごめんね、ひさしぶりに起きたから、ただちょっと気分が悪かったの。でも、僕もうだめかもしれない。さんちゃん!さんちゃんだけでも日本に帰ってね、死んで、たましいになって、さんちゃんを守ってあげる」 「いやだよ!たっちゃんがんばるんだ、元気をだしてたっちゃんの落語を聞きながら帰るのを楽しみにしているんだよ、ね!わかった」 たっちゃんは、自信なさそうに、軽くうなずきました。 さんちゃんが、たっちゃんとお話したのは、これが最後でした。 翌朝 たっちゃんが、体に何も身につけず、まる裸のまま死んでいました。でも満足そうなきれいな、死に顔でした。 何故、たっちゃんは、まるはだかで死んでいったのでしょう? 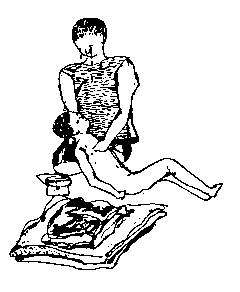 たっちゃんの下着と上着・長ズボンとお父さんの形見だといって、大切にしていた軍隊用の毛布は、きれいにたたんで、さんちゃんの枕もとに置いてありました。 それが、たっちゃんの最後の感謝の気持ちだったに違いありません。 さんちゃんの服装は、まわたい(麻袋を頭と両腕を通すところを作った上着)夏の半ズボンだけでした。死んだたっちゃんは、この服装では、寒い新京の冬を生きのびる事は、できないと思ったのでしょう。 きっと死をさとった、たっちゃんは、いま持っているすべての力をだしきって、上着と長ズボンと下着をぬぎ、きれいに、たたんでお世話になった、たっちゃんの枕元においたのです。それに、毛布と。 このことに気がついた、さんちゃんは、まる裸になった、たっちゃんのなきがらを抱きしめ、 「たっちゃん!僕はたっちゃんの親友なんだ!ラーメン食べて元気になってほしかった。一緒に日本に帰ろうと約束したじゃないか、一緒に‥‥ それに、裸までなって、ぼくに‥僕に最後まで、気を使って‥‥ たっちゃん 寒かったろうね、寒かったろうね‥ほんとに寒かったろうね!」といって、泣きじゃくりました、さんちゃんの大つぶの涙が、たっちゃんの唇をぬらしました。ちょうど、たっちゃんの死に水をとるように 新京の街にも、最初の寒波がやってきて、収容所の窓ガラスには、氷の花模様をつけました。 さんちゃんの泣き声だけが、まだ早い朝のよどんだ空気をふるわせていました。 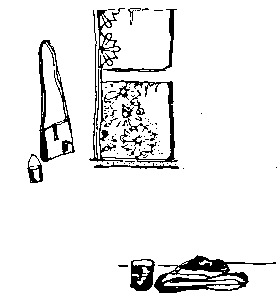 |